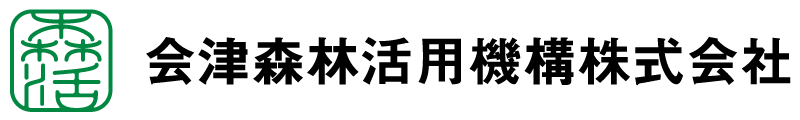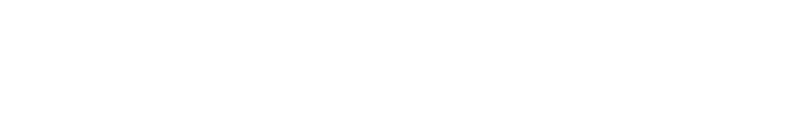森は、様々な働きを通して地球温暖化防止や生物多様性の保全など、私たちの生活の安定や経済の発展に寄与しています。たとえば、木材やきのこを生産し、いろいろな動物の住処にもなっています。水を貯え、きれいにし、生活環境を快適にします。さらに文化や景観を形作り、レクリエーションの場にもなります。
そんな森に関わる仕事が林業です。会津森林活用機構では、木材需要等の新たな価値の創出を目指すなど、林業のさまざまな可能性を探り、未来へ続く林業を築いていきます。
森の循環サイクル
育苗
日本では、山に種を蒔いて木を育てるのではなく、苗木を育て山に植えます。木から採取した種子を選別し、一般には育苗箱で発芽させ、その後ポット容器に植え替えたり、あるいは「苗場(苗畑)」と呼ばれる場所で苗木に育てます。これらの方法では通常、山に植えるまで2~4年かけて育てます。
南会津育苗センターでは、現在30万本の苗を出荷しています。


植林
苗木を山に植栽(植え付け)する前には、雑草や灌木を取り除く「地拵え(じごしらえ)」という整地作業を行います。これによって苗木の生育環境が良くなる、大事な作業です。「植栽」は春や秋、あまり暑くない時期に行うことが多く、苗木は山の斜面に手作業で1本ずつ植えます。
また、苗木はある程度密集させて植えた方が、生存競争が起こるために早く、まっすぐ上に向かって伸びます。


間伐
植栽してから数年は、苗木の生長を妨げる植物を除去する「下刈り」の作業を行います。下刈りを行わないと、せっかく植えた苗木が雑草の影になって枯れてしまうこともあります。さらに、苗木にからまる植物のツルや灌木の除去も行わなければなりません。
そして順調に樹木が成長すると、林の中は混み合ってしまいます。そこで、植えた木の本数を減らし、残された木が健全に育つように「間伐」を行います。


主伐
植えてから最低でも40年、スギの場合は植栽後50年前後で主伐の時期を迎えます。伐採の方法としては、一度に全部切ってしまう方法と一部分ずつ切り、また苗木を植えるという方法があります。こうすれば山には若い木が残りますから、森林の働きが衰えることもありません。
伐採した木は利用しやすい長さに切られ、丸太となり、運び出されます。


森を活用した関連事業
苗販売
当社育苗プラントで主にカラマツの苗木を年間30万本生産しております。苗は自社での植林に使われるほか、今後は苗の販売も積極的に行なってまいります。
熱供給事業
まとまった熱需要のある公共・民間施設へ木質バイオマス燃料を利用したボイラー設置や熱供給を行い、地方創生・福島の復興を目指します。
木質バイオマス発電
木質バイオマス資源を再生可能エネルギーとして活用することで、森林資源の保全と地域経済循環、さらには低炭素社会実現に貢献いたします。
製材加工販売
間伐材等を製材・販売し、森林の再生や循環を促進します。
地元産の木材を使用した地産地消の家づくりから大型の公共施設まで対応可能です。
木製品製造販売
地元の木材を利用した家具や雑貨などを製造・販売することで木材の地産地消を進めると同時に、関連産業を育成し雇用拡大を目指します。